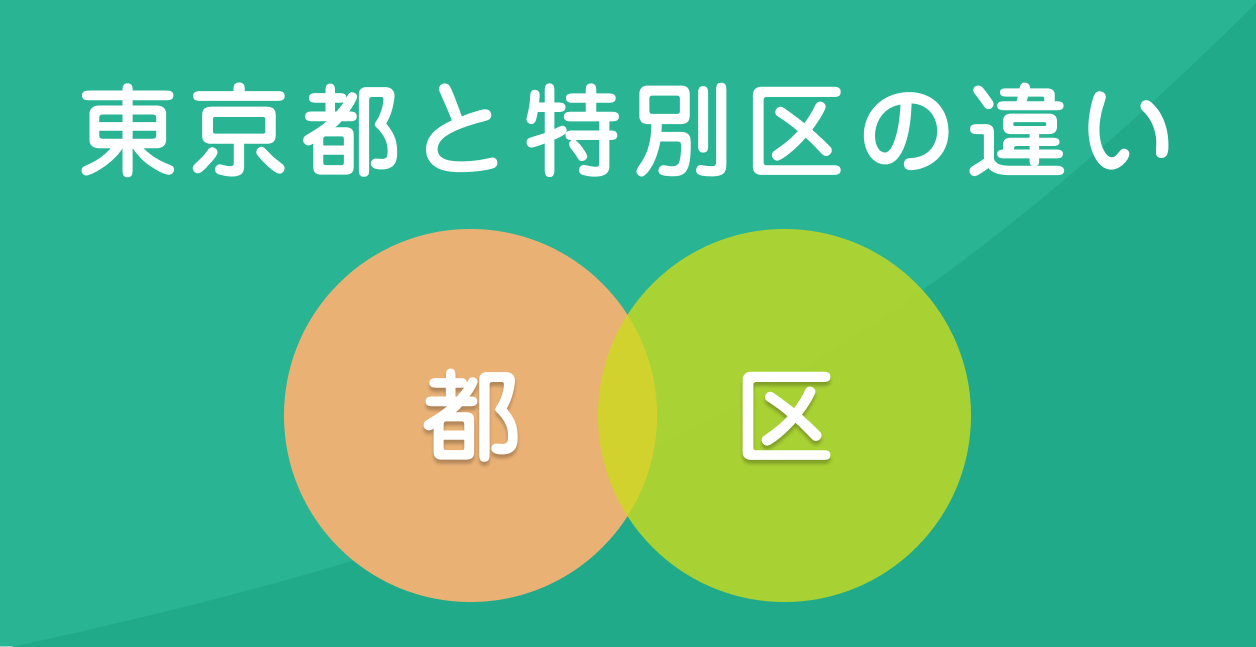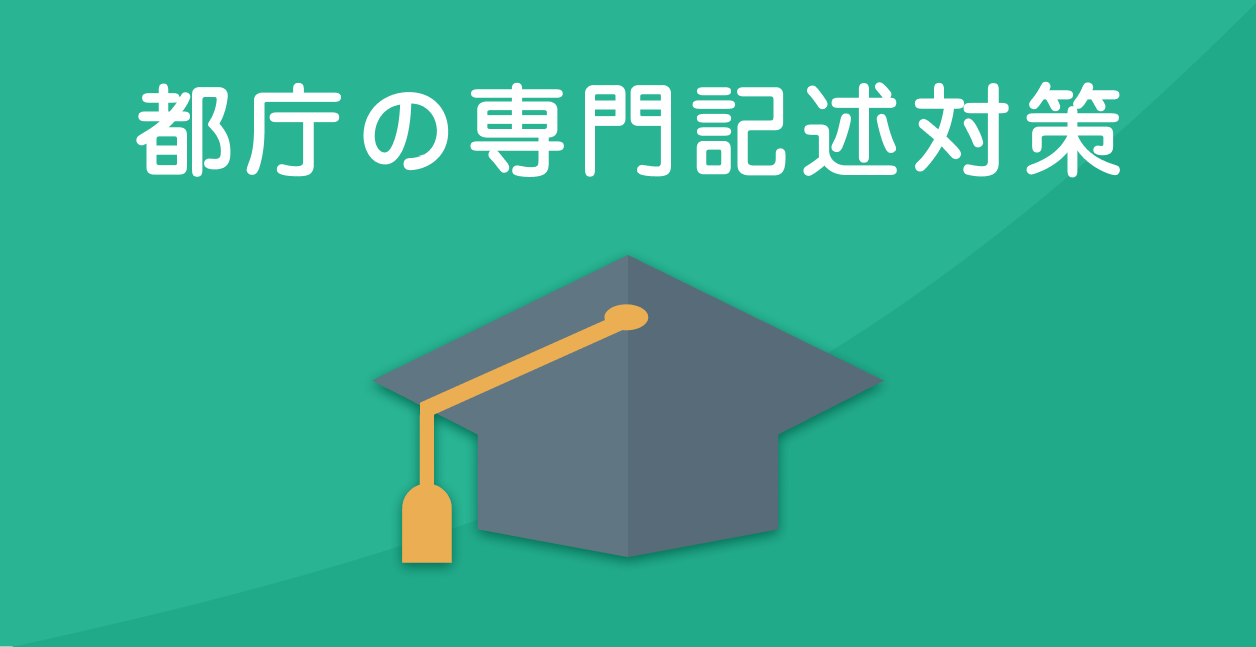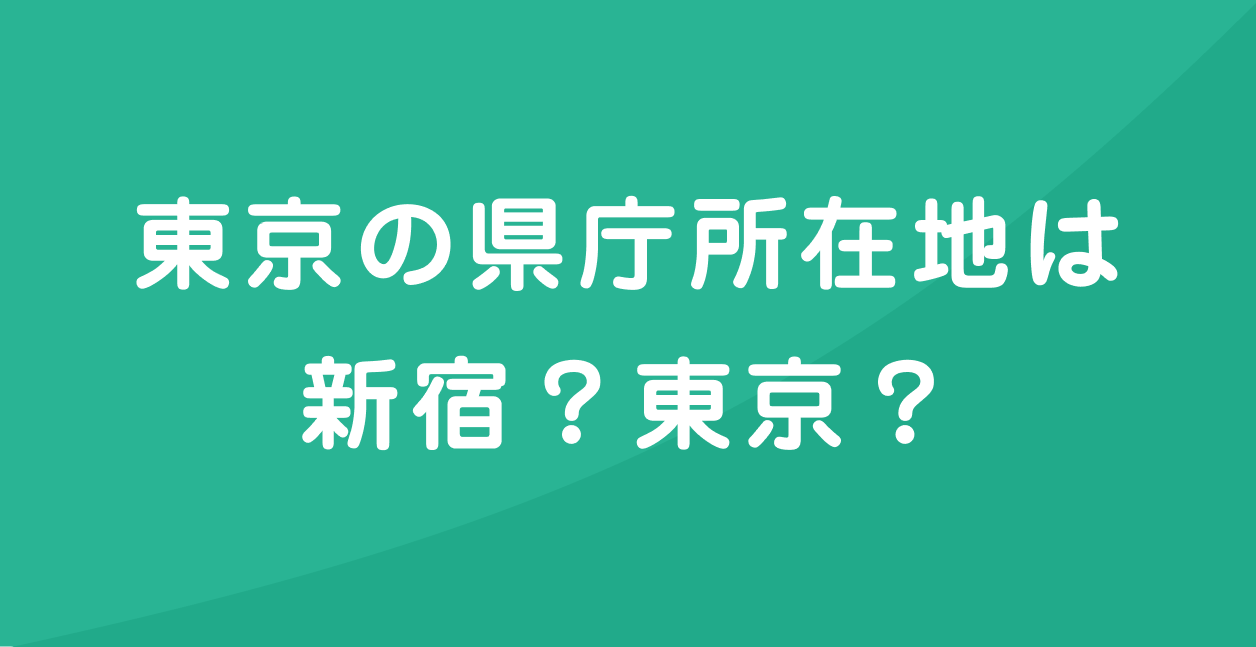元都庁職員のイクロです。
この記事では、東京都庁と特別区の違いについて、組織・仕事・採用という3つの観点から解説します。
東京都庁と特別区の組織上の違い
東京都庁と特別区の違いを、まずは組織という観点で見ていきます。
広域自治体と基礎自治体の違い
東京都と特別区の関係は、一部の面を除き、道府県(広域自治体)と市町村(基礎自治体)の関係と同じです。
- 東京都
- 広域自治体として、全県にわたる広域的な課題に取り組む
- 特別区
- 基礎自治体として、住民に身近な行政機関の役割を果たす
ただし、特別区は指定都市や中核市と同様に「大都市制度」による自治体であり、一般の市とは管轄領域の広さに違いがあります。下記は東京都による特別区の説明です。
わが国の地方自治制度は、原則として市町村と府県とによる二層制を採用しています。
しかし、交通、環境、防災・安全、インフラ整備など、都市特有の問題について膨大な行政需要を抱える大都市においては、市町村、都道府県という画一的な事務配分のもとで的確な対応をすることが困難となっています。
そこで、現在の地方自治法は、大都市制度として指定都市、中核市の各制度と特別区制度を採用しています。
指定都市、中核市の各制度は、市が府県の行う事務の一部を担うのに対し、特別区制度は、特別区が一般的に市町村が行う事務を行うとともに、都が大都市行政の一体性及び統一性を確保するために必要な市の事務の一部を担うというものです。
つまり、特別区は普通の市よりも管轄が狭いということです。普通であれば市町村が担当する領域も、特別区でなく東京都が担当する場合があります。
具体的には、水道・下水道、消防は通常は市町村の管轄です。しかし、東京では特別区の各区ではなく東京都が担当しています。
歴史的には、もともと特別区は東京都の内部組織という色が強く、徐々に権限移譲を受けた結果、基礎自治体として定義されるようになったという経緯があります。以下は、公益財団法人特別区協議会による説明です。
昭和27年の地方自治法改正では、特別区は東京都の内部的な団体とされ、区長の公選制も廃止されてしまいました。その後、特別区は自治権拡充運動を展開し、区長公選制の復活をはじめ、数度の改革が行われました。そして、平成12年、地方自治法に『特別区は「基礎的な地方公共団体」』と明記され、今日に至っています。
総じて、一部で一般的な広域自治体と基礎自治体との役割分担とは違いがあるものの、基本的には東京都は道府県・特別区は市町村だと捉えて問題は無いでしょう。
組織規模の違い
広域自治体と基礎自治体という違いは、当然組織としての規模にも影響しています。
例えば、特別区である千代田区の職員数は1,090人(2018年4月4日)です。それに対して、東京都は38,537人(2018年01月26日)と、約35倍の差があります。民間企業で例えると、特別区の各区は中規模の企業、東京都は大企業ということになるでしょう。
次のページ 東京都庁と特別区での仕事の違い