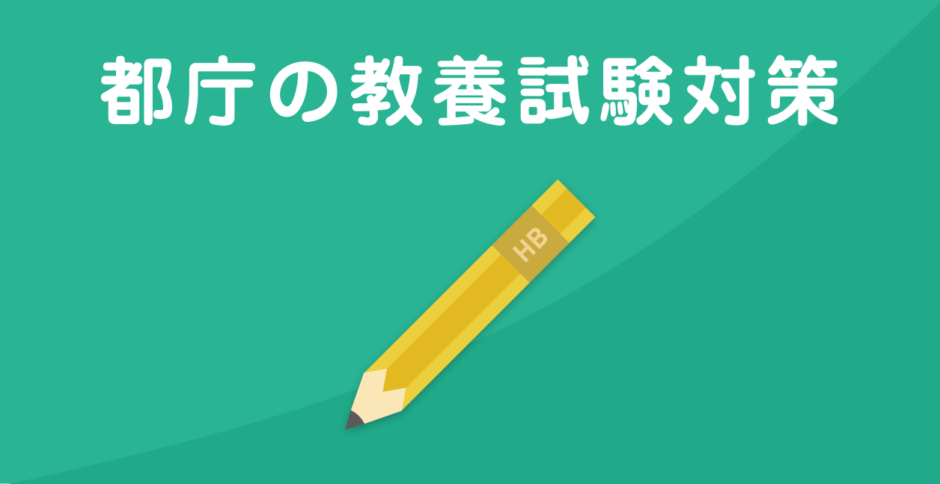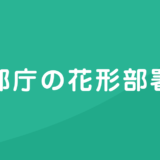元都職員のイクロです。
この記事では、都庁の受験生向けに教養試験対策(択一)について解説します。都庁の採用試験において教養択一は非常に重要です。正しい戦略を理解して、合格を勝ち取りましょう。
都庁の教養択一でボーダーを下回ると足切りになる
都庁の受験生であればご存知の方が多いとは思いますが、都庁の教養択一にはボーダーラインが毎年設定され、それを下回ると他の試験の点数に関わらず足切りになってしまいます。
ボーダーラインは相対評価なので年により異なりますが、24 ~ 26 / 40になることが多いです。場合によっては30点などかなり高い水準になることもあります。
ここで足切りになると、いくら教養論文や専門記述が完璧でも問答無用で落とされるため、都庁の試験対策ではまず教養択一の準備を万全にすることが極めて重要です。
下記で、足切りを突破するための戦略について解説します。(前提として、ご自身が文系・理系どちらなのかや、元々の得意科目・不得意科目が何なのかによって戦略は異なってきます。ここで解説するのは一般論としての戦略なので、これをベースにしつつご自身に合うかたちでカスタマイズしていただくとよいと思います。)
教養の科目の配点
平成31年度、1類B一般方式、技術以外。出典:東京都職員採用
| 科目 | 出題数 |
| 数的推理(数的処理・空間概念) | 10 |
| 判断推理 | 2 |
| 資料解釈 | 4 |
| 文章理解 | 4 |
| 英文理解 | 4 |
| 歴史 | 1 |
| 文化 | 2 |
| 地理 | 1 |
| 法律 | 1 |
| 政治 | 1 |
| 経済 | 1 |
| 物理 | 1 |
| 化学 | 1 |
| 生物 | 1 |
| 地学 | 1 |
| 時事(社会事情) | 5 |